|
|
 |
徳島に何故ドイツ館
第1次世界大戦に日本も参戦し、ドイツの
租借地だった中国の山東半島にある青島
を攻撃し、敗れたドイツ兵士約5,000人が俘
虜となり日本各地の収容所に送られた。
その内四国の徳島・丸亀・松山にいた
約1,000人が1917(大正6)年から1,920年
までの3年間を板東俘虜収容所ですごした。
その縁で1,972年に旧ドイツ館が建設され
1,974年には鳴門市とドイツ・リューネブルカ市
との間で姉妹都市盟約が締結された。
|
|
 |
ここは第九のふるさと
地域の人々は俘虜たちの進んだ技術や文化を取り
入れようと、牧畜・製菓・西洋野菜栽培・建築・音楽・
スポーツなどの指導を受け、
俘虜たちを「ドイツさん」と呼び日常的に交流していた。
この板東俘虜収容所の松江豊寿所長は会津出身で
戊辰戦争で辛い思いをしているので
「俘虜は犯罪者ではない。彼らも祖国のために立派に
戦ったのだから、武士の情けをもって遇したい」
との信念で出来る限り自由な活動を許した
偉大な所長として知られているそうです。
音楽面では定期的にコンサートも開かれていたようで
ベートーヴェンの交響曲第九番を日本で初めて
全楽章を演奏したことが有名です。 |
|
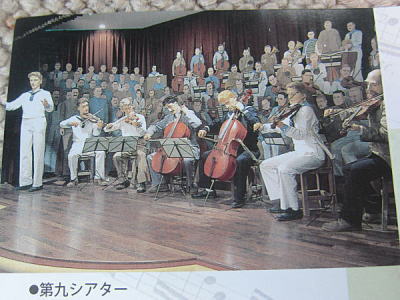 |
第九シアター
当時のドイツ兵たちの音楽活動が紹介されている。
等身大の人形が、15分間演奏を聴かせてくれました。
|
|
 |
|