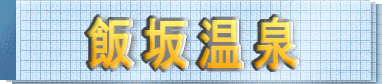 |
 |
 |
福島県を南北に流れる阿武隈川の支流摺上川沿いに
位置する飯坂温泉は、旅館やホテル、共同浴場が立ち
並ぶ東北を代表する一大温泉地。
日本武尊が東征の際に飯坂で温泉を発見し、傷を
平癒させたのが飯坂温泉発祥の由来という。
|
|
|
 |
時代は下がって「奥の細道」の旅に出た松尾芭蕉は1869年飯坂の湯に浸かっています。
 駅前の松尾芭蕉の像 駅前の松尾芭蕉の像
江戸時代から幕末にかけては近隣の諸藩の武士にも親しまれ賑わいました。
明治以降一貫して発展を続け、1965年には磐梯吾妻スカイラインが開通、団体旅行客が訪れるよ
うになり、高度成長時代の温泉街は、連日歓迎の打ち上げ花火が上がるほど賑わったようです。
時代は変わり、温泉へのニーズが団体旅行から個人で楽しむ旅行へと変化し、
温泉街の随所に閉鎖している宿泊施設や商店が多くみられました。 |
|
 |
 |
 |
温泉街から少し奥まった静かな一角にある摺上川を
見下ろす川岸の宿「小瀧館花静」
「花」と「静」をテーマにした館内は琴の音が流れ
随所に花が飾られています。
皇太子殿下ご夫妻も泊られたようです。 |
|
    |
|
|
 |
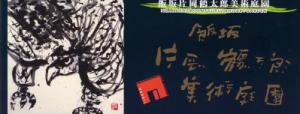 |
片岡鶴太郎美術庭園
飯坂温泉の隣り花水坂駅前に2004年10月に開館した、
鶴太郎氏の絵画や陶器などを展示する美術館。
吹き抜けの館内にはゆったりと作品が展示され、創作活動
をするアトリエもあり、落ち着いて鑑賞できる美術館です。 |
|
 |
 |
 |
| 館内 (パンフレットより) |
館内にある銀座絵島花水坂店 |
鶴太郎氏の作品(ポストカードより) |
|
|
|
 |
1月にNHK文化センターの地元学講座を受講した時、義経の本当の家来は佐藤継信、忠信の二人だけだった
という話を金野精一氏から聞きました。飯坂温泉の近くにこの二人の菩提寺があることを知り訪ねてみました。
花水坂の隣の医王寺前駅に下りて辺りを眺めていたら「医王寺に行くなら私についてきて」と声をかけてくれた親切なおば
さんについて7〜8分歩いた所にありました。案内板もなく、連れて行ってもらわなかったら真っ直ぐには行けませんでした。
境内は整備されていますし、300円の拝観料も取っている所なので義経ブームにのって案内板でもあればと思いました。
|
 |
医王寺
828年の創建。この地方を信夫といい、信夫の荘司といわれた佐藤基治公
が当地の大鳥城を居城としていて、この寺を菩提寺としていたそうです。 |
 |
|
|
平泉の藤原秀衡のもとにいた源義経が源平合戦への旗揚げをした時、基治公は子の継信、忠信の二人を遣わしました。
兄継信は屋島の合戦で義経を射ようとした能登守教経の矢を盾となって受け、弟忠信は頼朝に追われた義経を京都堀川
で義経を名乗って敵を引きつけ主君を逃がし討ち死にしました。
その後義経一行が弁慶とともに平泉に向かう途中、この寺に参籠し遺髪を埋めて二人の追悼の法要を営んだそうです。
1689年芭蕉は「奥の細道」の行脚で当寺を訪れ、伝え聞いた佐藤兄弟の墓を詣でています。
謡曲「摂待」はこの佐藤兄弟の遺族を中心とする忠孝の情を描いた曲だそうです。 |
 |
 |
| 佐藤兄弟の両親基治・乙和の墓 |
佐藤継信・忠信の墓
|
|

 |
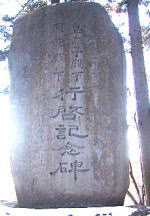
皇太子夫妻も訪れる |
 |
宝物殿
弁慶の笈や義経の着物の端と
いわれる布もありましたが・・・・ |
|
|
乙和椿
基治・乙和の墓の傍らにある椿で、樹齢数百年でつぼみが色づけば落ち一輪も花を開かないので、
母親の悲しみが乗り移ったとして乙和椿と呼ばれるようになったそうです。 平成17年2月12〜13日
|
 |