 |
利根川源流に近い支川・楢俣川に建設され、分水嶺の直下(標高約900m)にあり、岩塊を台形に積み上げるロックフィル式の
ダムで、洪水調節・下流の都市の水道用水・農工業用水の供給などを目的として作られた多目的ダムで、
約8年の歳月をかけて平成元年に完成し、東京の水ガメにもなっているそうです。 |
|
|
|
|
 |
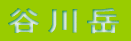 |
日本百名山、谷川岳は標高1,963mのトマノ耳と1,977mのオキノ耳の”耳二つ”のことをいい、上越国境沿いに結ぶ谷川連峰の
中心的存在にあたります。日本屈指の岩場で、その特殊な地勢と気象は日本アルプスの3,000m級の高山に匹敵するパノラマ
を誇ります。上級登山者向きの山と思われますが、ロープウェイとリフトを利用すれば比較的楽に登れます。(パンフレットより) |
 |
一ノ倉沢
日本三大岩壁の一つで、
夏でも消えない万年雪。
目の前にそびえた
雄大な景観に感激。
沢の流水は手を浸して
いられないほどの冷たさでした。 |
 |
|
|
 |
谷川岳ロープウェイ
標高1,321mの天神平駅まで約10分で一気に駆け上がる。
窓越しに広がる雄大な360度の大パノラマが楽しめます。
6階建て、収容台数1,000台(総収容2,000台)の大型屋内
駐車場に車を駐車させ、ロープウェイに乗り、下を見ると
怖くなるような高さでしたが快晴の大パノラマを楽しみました。 |
|
天神平駅からリフトで
リフトに乗って
5分間の眺望を楽しみながら天神峠展望台へ |
天神平展望台からの眺望
平安初期に開山し、約一千年の歴史をもつ霊山・谷川岳。
昔の登山者は途中天神峠で休み、沼の水で身を清めたといいます。
今、峠に「諸天善神」が祀られ、鳥居が建てられています。 |
 |
 |
|
 |
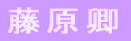 |
水上温泉にある藤原卿落人の歴史
今から750年前源頼朝によって滅ぼされた藤原泰衡の子孫海飽太郎が一族を率いて尾瀬を越えて奥利根のこの地を開いた。
関東平野の人々を救うため160戸が昭和33年に完成した藤原ダムの湖の底へ沈みました。 |
湖底の故郷館
藤原ダム45年の歴史が展示されています。 |
400年の歴史ある茅葺きの家
ここが湖底の故郷館になっています。 |
 |
 |
|
郷土館
ここ落人の里の歴史が展示されています。 |
落人料理「ざるめし」
奥州平泉より落ちのびる時、食器がないため朴の葉や、
熊笹をざるにのせて常食としたそうで、それを再現して
ざるにご飯、岩魚、17種類の山菜の煮付けを盛ったもの。 |
 |
 |
|
 |
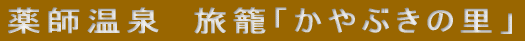 |
吾妻町にある薬師温泉「旅籠(ハタゴ)」、この温泉は1793年に発見され昭和5年に薬師温泉と名付けられたそうです。
その敷地内に茅葺きの屋敷、時代ものの陶器や家具、明治時代に鋳造された日本一の鉄大釜、
鉄道の枕木を使った物とかを様々集めて「かやぶきの里」として見学させている所。 |
 |
本 陣
茅葺きの広さ200坪の建物。
屋根の萱の厚さは1mと
重要文化財の寺社仏閣と並ぶ厚さがあります。
旅籠の帳場、くつろぎ処、土産処があります。 |
|
枕木街道
全国から集められた20,000本の枕木で作ってある街道。
ここを通って本陣へ。 |
枕木広場と枕木茶房
枕木をリユースして作った広場で、
この日は餅つきのイベントがあり、黄粉餅が振舞われました。
枕木茶房はくつろぎの空間で手打ちのそばを食べました。 |
 |
 |
時代もの展示処
古伊万里、貝合わせの貝、火縄銃などの古具が展示されてる。 |
招福七連鐘堂
七つの鐘があり、
想いを込めてそれぞれの鐘を叩けば願いが叶うとか。 |
 |
 |
南部曲がり屋「木村家」
1855年に建てられたもの。 |
出羽の国「紺野家」
山形県のかっての庄屋の三階建ての大屋敷。 |
 |
 |
|
 |