 |
| 平成18年4月1日 盛岡駅より新幹線「やまびこ」で郡山まで行き「なすの」に乗り換えて那須塩原駅へ |
 |
黒磯巻狩鍋
駅前に大きな鉄鍋がありました。
鎌倉時代、将軍が狩をするとき武将22名、
勢子10万人、5千余騎の参加で鹿、熊、
狐等約2500頭の獲物があったといわれる
そうで、これを思わせる鍋料理を郷土食
として供することを考え、毎年10月に
「那須野巻狩まつり」として7市町村に
あるこの大将鍋を一ヶ所に集めて
鍋料理が供されるそうです。 |
 |
|
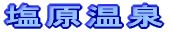
塩原に人が住み始めたのは、縄文中期頃といわれていて、温泉は平安時代806年に発見されたと伝え
られているそうです。箒川(ほうきがわ)ぞいに11の湯元があり「塩原十一湯」と呼ばれているようです。 |
 |
 |
 |
塩原もの語り館
温泉街に関する情報を提供している
塩原温泉協会の案内所。
展示室では塩原の歴史、風の人(訪れた人)、
土の人(出身者)等を詳しく紹介し、
2階にはカフェレストラン「洋燈」もあり、
作りが面白い館でした。 |
|
|
|
天皇の間記念公園
大正・昭和天皇や皇族が避暑地としていた旧塩原御用邸の一部(天皇の間と呼ばれる御座所))を移築、保存している。
塩原御用邸は明治16年栃木県令となり、那須野ヶ原開拓事業等を行った三島通庸が作った別荘で、
息子三島弥太郎(後の日本銀行総裁)が皇室に献上し、明治37年に「塩原御用邸」となったものです。
戦後御用邸は廃止されこの天皇の間だけがここに移築され、御用邸は「国立塩原視力センター」として
視力障害者の教育施設として活用されているそうです。 |
 |
|
|
 |
 |
塩原十一湯の一つである
福渡温泉の松楓楼松屋に泊まる。
明治11年創業で、かって福渡に大正天皇の御用邸
があった頃は御用邸を訪れる宮中の方々の
お料理を調理したこともあり、田山花袋、
柳田国男など文人の訪れた宿でもあるそうです。 |
|
翌朝5時半頃目が覚めたので窓の下の箒川を見てビックリ。大勢の釣り人が川の中に入っているではありませんか
見ているとけっこう大きいのが釣れていました。せっかくなので川沿いの遊歩道を散歩してみました。 |
 |
|
|
|
|
 |
緑色凝灰岩
今から2000万年前は塩原は海底火山の
爆発が続く海底にあり、そこに大量の
火山灰などが積もってできた岩で、
あざやかな緑色が特徴なそうです。 |
 |
|
 |
殺生石
謡曲や歌舞伎の題材となっている殺生石史跡の一つ
平安初期金色の毛、九本の尾をもつ狐がいました。アジア大陸を暴れまわり悪行をつくした後、日本にやってきました。
美しい女官に化け帝に仕えているところ正体を見破られ那須野が原に逃げました。ここでも悪事をはたらき人々は困り
果て、朝廷は軍勢でこの狐を矢で射ると大きな石となりました。石になっても猛毒をふるって人々や獣までもいじめた
ので、名僧が毒石に経をあげると三つに割れて飛び一つがここに残った。人々は毒石を恐れて「殺生石」となずけた。 |
 |
 |
湯の花採所
湯の花とは「みょうばん」のことで、
徳川幕府の頃から那須温泉の人々は年貢米の
代わりに湯の花を納めていたそうです。
殺生石はここから300m位上にあるそうで
附近は今でも亜硫酸ガスや硫化水素、炭酸ガスを
噴き出しているそうです。
那須山の活動とともに以前は噴気を吹き上げていたので
その様子を地獄と思い無限地獄と呼んだようです。
|
|
 |
盲蛇石
昔、ある湯守が山に薪を採りに行った帰り道、
殺生河原で大蛇に出会い、盲の蛇でかわいそう
に思って小枝で小屋を作ってあげました。
翌年来て見ると蛇はいなくなってキラキラ輝く
湯の花がありました。その後湯の花の作り方が村
中に広まり、村人は盲蛇に感謝するため、蛇の首
に似たこの石を盲蛇石と名付け大切にしたそうです。 |
|
千体地蔵
行いの悪い子を心配した母親がお坊さんにしよ
うと寺に預けました。その後住職になりましたが
行いはなおりませんでした。ある日母親をいじめ
た後友人と一緒に那須温泉に湯治に行き、
殺生石を見ようとこの賽の河原附近まで来た
とき、雷鳴がとどろき、火炎熱湯が噴き出し、
逃げられなくなりました。その後温泉の有志が
地蔵を建立して供養し、親不孝のいましめと
して参拝者が後を断たなかったそうです。
とても奇妙な光景でした。 |
 |
|
| 殺生石 での松尾芭蕉の一句「石の香や夏草赤く露あつし」 |
 |
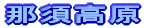
那須岳の南麓に広がる高原リゾート地。高原中央の那須街道沿いには
個性的な美術館やテーマパークが点在していて、
看板も自然に溶け込むように茶や黒系統の落ち着いた色に統一されていました。 |
  |
|
那須ステンドグラス美術館
100〜150年前のイギリスを中心としたヨーロッパのアンティークステンドグラスを展示した美術館。
ライムストーンを使った石積みの外観で、スレート屋根瓦、鉄の門扉、外灯すべてイギリスからの直輸入
で建築されている。ステンドグラスは45作品が展示されている。館内には3つの礼拝堂があり、それぞれの窓には
ヨーロッパ各地で作られたアンティークステンドグラスがはめ込まれ、一つではオルゴールの演奏、
一つはパイプオルガンの演奏が行われ、一つだけが館内でただ一ヵ所撮影が許可されている所でした。 |
|
|
|
|
 |
| みちのく諸国郷土民芸館 |
|
|
 |
| アジアン・オールドバザール |
|
|
|
|
| たった2日間の旅でしたがレンタカーを借りたので結構回って見ることができました。 |
 |
|
|