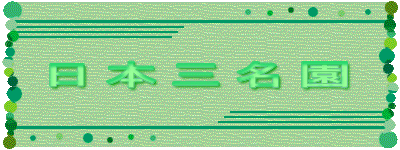 |
|
|
日本の三名園といわれる水戸の偕楽園、金沢の兼六園、岡山の後楽園
訪れた時期は違いますが、三名園とも見ましたので思い出しながら纏めてみました。 |
 |
水戸藩九代目藩主徳川斉明が自ら造園計画を練って作った庭園で、
藩内の武士の休息の場として開設されたものなそうです。
梅の木100種類3000本以上と梅の季節が一番有名です。 |
|
|
| 斉昭が茶を楽しむために造った「好文亭」最上階からの眺めが素晴らしい。 |
|
|
| 梅の季節はこのように美しいそうですが時季はずれなのが残念でした。 |
 |
 |
1822年加賀百万石前田藩12代藩主斉広が豪壮な隠居所(竹沢御殿)を建て、その庭に奥州白河藩主に園の命名を依頼しました。藩主楽翁は中国宋の時代の詩人、李格非の書いた洛陽名園記の文中から採って、宏大(こうだい)・幽邃(ゆうすい)・人力・創古(そうこ)・水泉・眺望の六勝を兼備するという意味で「兼六園」と命名しました。
13代藩主は竹沢御殿をとりこわして霞ヶ池を掘り広げ、あらたな曲水をとりいれて以前からあった蓮池庭と調和する様に造園し、江戸時代を代表する林泉回遊式庭園が完成し、そのまま今にのこっています。
明治7年一般に開放され、昭和60年には特別名勝に指定されました。 |
|
|
| 1995年6月に訪れたときの写真です。 |
 |
林泉回遊式庭園とは
池・築山・曲水・樹林など移り変わる景色を眺めて一回りすると、一巻の絵巻物を見て終わるという趣向になっている庭園 |
有名な唐崎松の雪吊り(パンフレットより)
兼六園の雪吊りは180種800本の樹木 |
|
|
  |
1686年岡山藩主池田綱政公が造園を命じて14年の歳月をかけて完成した林泉回遊式庭園。
藩主の静養の場、賓客接待の場として使われ、時々藩内の人々にも観覧が許されていたそうです。
岡山城の後に造られた園という意味で後園と呼ばれていましたが1871年に後楽園と改める。
1884年(明治17年)岡山県の所有となり一般に公開されました。
園内から岡山城以外の周囲の建物が見えないのは周囲のビルに高さ制限が設けられているためなそうです。
日本庭園でありながら芝生が敷かれているのが特徴で、日本で初めて芝を大量に使った庭なそうです。 |
 |
 |
|
| 岡山城は黒い下見板張りの外観から「烏城(うじょう)」とも呼ばれています。 |
|
 |
 |
|
| 岡山城を望む |
お姫様になった気分で |
|
|
 |